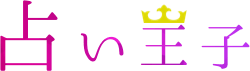神社に参拝していて「玉串料」という言葉を聞いたことがあるという人はいませんか?ここでは、玉串料とは何かについてご紹介します。
神社等でこの言葉を見た事があるという方も無い方も是非参考にして下さいね。
1.玉串とは
玉串料で使われている玉串ですが、神社で儀式をする時に使われています。
榊の枝に紙垂を付け、垂らしたものが玉串です。
神社の儀式の際に見た事があるという方も多いでしょう。
神様に捧げるものですので、非常に重要なものです。
そしてこの玉串は神様と人を繋げるものだと言われています。
榊が使われる事が多いですが、その土地によって使われている枝は違います。
沖縄ではガジュマルが使われる事もあるそうです。
玉串の由来ですが、日本神話に出てくる天照大神が使用していた事がきっかけではないかという説が有力です。
また、玉串という言葉の由来ですが、様々な説がありはっきりとした答えは分かっていないそうです。