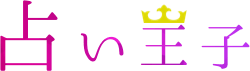お守りを持っていると、神様がそばにいて守っていてくれるような気になります。
小さいですが、お守りのパワーというのは大きく、安心できます。
ただ、お守りの中がどうなっているのか気になっても、決して開けてはいけません。
その理由を知っておけば、きっと「なるほど」と思えて、気持ちを納得させることができるでしょう。
1.お守りを開けてしまうことは神様に対して失礼だから
お守りを開けてはいけない理由は色々あります。
そしてその中でも最も重要なのは、お守りを開けて中を覗いてしまうことは、神様に対して失礼にあたるということです。
お守りの中身は、通常木札と言われる小さな木の板で、神様や仏様の名前を墨書きした紙が入っています。
この木の板こそ、神様とつ奈がっていると考えられています。
いわば神様そのものでもあると言えるでしょう。
それなのに、お守りを開いて中を見てしまうということは、神様を「裸」にしたのと同じとなります。
お守りは、持つ人の身の安全をはかってくれたり、願いを叶えてくれるものです。
しかし、その大切なお守りを開けてしまうことは、好奇心に負けて神様に対して失礼なことをしたと考えられるので、決して開けてはいけないのです。