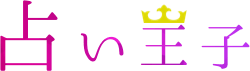初詣は、子供の頃から行っている人がほとんどですが、行く意味や細かな目的を深く考えるケースは少ないです。
そこで、初詣の意味・由来・いつまでに行けば良いか解説します。
1.初詣の意味
初詣の意味自体を調べると、新年を迎えてから初めて神社や寺院へお参りに行くことです。
言葉の意味自体はシンプルですが、初詣には他にも色々な意味があります。
1つは旧年の感謝を神様に伝える意味があり、次に新年も宜しくお願いしますという願いの意味があります。
いづれの意味も神様に対する祈願となっていて、健康や安全、願い事などを神様にお願いする行為が初詣の意味の深層部分です。
若い世代だと初詣に行って参拝する際、新年の祈願のみする人が多いですが、旧年の感謝をする意味もあるので、旧年・新年を合わせた参拝方法が初詣の意味に沿っています。
また、神社の神様は家の正月飾りに宿る神様と種類が違い、不特定多数を対象にした神様となっています。
家の正月飾りに宿る神様は、先祖など特定の人を対象にした神様の意味があり、自宅で神様に新年を祈願したから初詣は完了とはなりません。
その為、毎年行う初詣は神社や寺院に行く必要があり、自宅で行う新年祈願は先祖に感謝するなど違う意味を持っています。