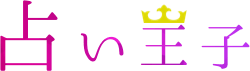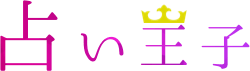蓮の花は、仏教に関係した花言葉が多くあります。
泥水の中から清らかで美しい花を咲かせる様子が、悟りの達した者の知恵の象徴とされているからと考えられます。
また良い行いをした者が、死後に極楽浄土に行き、蓮の上に身を置き生まれ変わるという考え方もあります。
一蓮托生と言う言葉は、蓮の上に生まれ変わることを表しています。
今回はそんな蓮の花言葉を解説します。
次のページヘ
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
【蓮の花言葉】白/赤/ピンク/青の蓮の花言葉を解説しますに関連する占い情報